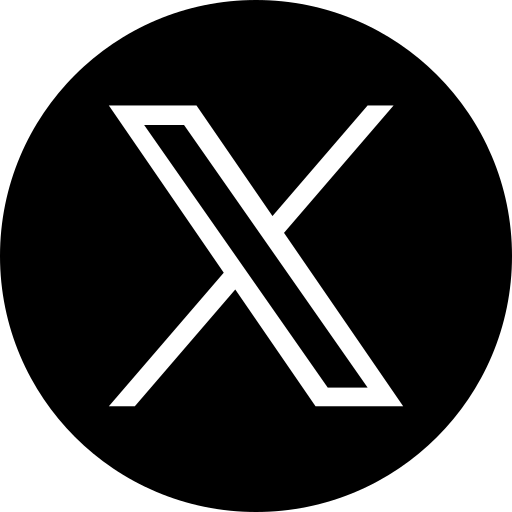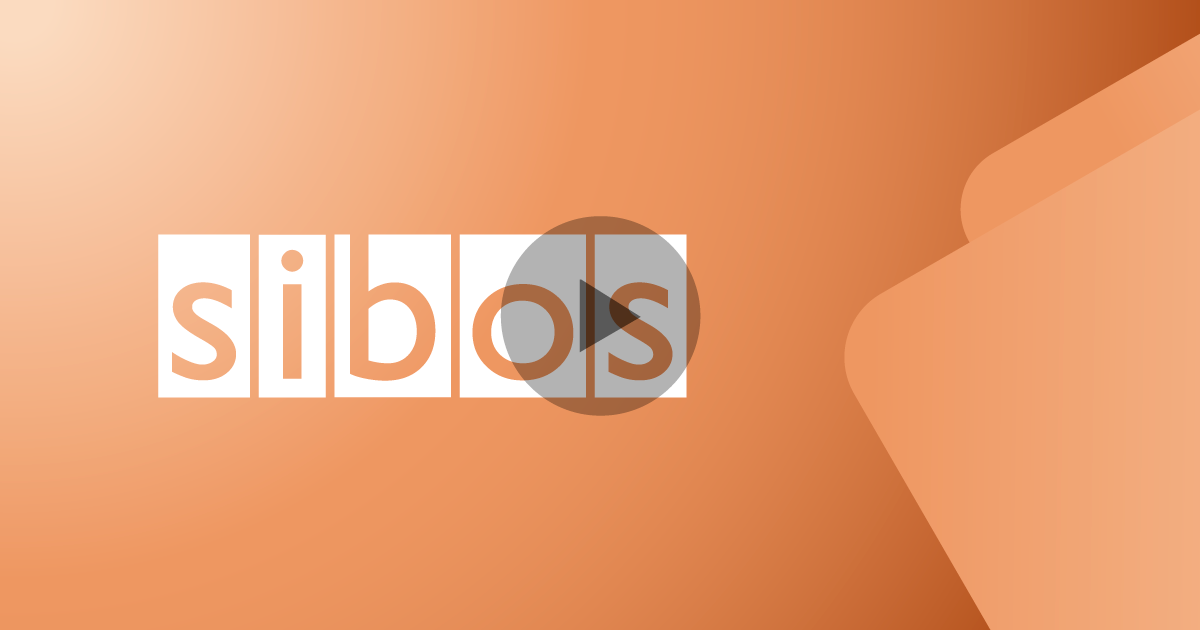金融規制当局の役割は、通貨や管理、また監督のプロセスを増強するような新たな技術を持続的に取り入れ、時代に合ったものにしていくことにあります。そのうちのひとつが「小切手」です。将来的な支払いを確約するツールとして小切手が法人および小売客の間で用いられていることから、この機能を刷新していくことは金融界における非常に重要なミッションだといえます。
小切手が重要なものであることを示す根拠はいくつか考えられます。例えば、直接的な負債による支払いには欠点が存在すること、即時決済だと限界があること、また小切手を介した支払いが非常に安全であることなどが挙げられます。
しかし、小切手を決済手段を用いる上では、金融規制当局とユーザーの双方をアシストするような機能が必要となってきます。例としては、署名の不一致による小切手の差し戻しの削減や、支払いの受取人が受け取った小切手を入金と回収に先んじてオンライン・オフラインを問わず確認する方法の実現などが考えられます。これらの開発は、自筆の署名を電子暗号化技術に基づいた署名で代替するといった形で実現することができます。
ProgressSoftは世界で初めて国中に電子小切手を導入し、そこからさまざまな洞察を得てきました。今回のブログではこの経験をもとに、小切手の導入に関して前向きな変化を求める中央銀行にとって有益となる実用的なアドバイスをご紹介します。
導入プロセス
2021年10月、ProgressSoftは世界初となる全国規模の電子小切手ソリューションを稼働させました。通常、電子小切手のような革新的なソリューションを初導入する場合、登録ユーザーおよび取引量は非常に低いものとなることが推定されます。したがって、規制当局も、システムオペレーターも、電子小切手サービスをローンチした初日に何が起こるかを予期してはいませんでした。しかし、その初日、45,000もの銀行小売客がシステムへの登録を果たし、初となる電子小切手のリクエストを送信したのです。また、わずか5日後、およそ50万ものユーザーが登録し、国内の小切手のおよそ4.5%が電子小切手に置換されました。これにより、市場が電子小切手のソリューションを求めていたことが明らかになりました。
このサービスは、企業から中小事業、またひとり社長である会社など、法人客にも利用されました。法人客およびその認証された署名の適切な登録や、必要なKYC要項と認証マトリクスを含むより高度なセキュリティを導入できることが理由です。現在、今後数か月での登録法人数は50,000社以上になると予想されています。
成功要因
今回の導入の成功要因にはいくつかありますが、一例としては下記のものが考えられます。
ユーザー体験(UX)
電子小切手を活用することにより、使いやすさや反応性、主な目的の達成という面でユーザーの期待に応えることができたことは、今回の導入案件の成功にとって不可欠な要素でした。ユーザーは使い方の説明に沿ってスムーズに操作を進め、リモートでの登録、電子小切手のリクエスト、金額の入力から署名、共有、入金・資金回収までを完了することができ、これは非常に現代的なスタイルであると感じられる体験でした。
顧客への導入誘導
ある実装が成功したかどうかを決定づけるのはやはりエンドユーザーの存在です。こうして紙小切手から電子小切手への置換が実現する以前から、ユーザーは新たなサービスやチャネル、メカニズムが利用できるようになると告知されていました。これはマーケティング上の取り組みというだけではなく、カスタマーサービスのコールセンターおよびヘルプデスク機能を通じて、オペレーターが顧客からの問い合わせに答えられるようにするためでもありました。
マーケティング
オペレーターの準備を万全にすることと合わせて、適切なマーケティングを実施し、顧客に知られるきっかけとなるような取り組みをしたことも、サービスの導入が実現する一押しとなりました。ローンチ前には、新たなサービス、その特徴や機能、メリット、サービスの利用方法のステップバイステップのガイドについて周知が促されました。
結論
全国規模の電子小切手の導入を成功させるには、規制当局、オペレーター、銀行、そしてソリューションプロバイダーが、ビジネスおよび技術的なノウハウを身につけ、一丸となって導入に向けて動かなければなりません。また、銀行には法人のクライアント登録を完了し、新たなサービスを既存のチャネルに統合し、顧客教育と周知に優先的に取り組むことが重要になります。
最後に、面白い事実をご紹介しましょう。紙の小切手の印刷コストは、1000ページの小切手につき150〜200ドル程度です。つまり、毎日20万の小切手が切られる国では、毎年およそ1500万ドルが年間で小切手印刷に消費されていることになるのです。したがって、電子小切手の導入は市場に求められているのみならず、規制当局の望みでもあると言えるでしょう。